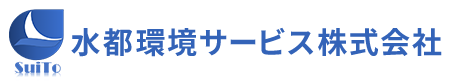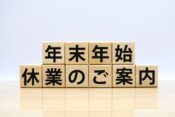BCP対策で一番に考えたい水設備の重要性とは

最近、地震や台風、水害などによる多くの被害が発生しています。そのため個人の家庭だけではなく、地域に根付いた企業にも災害対策が重要視されるようになってきました。
特に2011年の東日本大震災以降、大型商業施設や医療施設などで「BCP対策」という言葉が交わされるようになり、最近では中小企業にもBCP対策が求められつつあります。
そこで今回は、BCP対策の必要性や、BCP対策を考えたとき一番に対応を計画しておきたい「水」への対策についてお話していきたいと思います。
1: BCP対策とは
「BCP対策」という言葉を耳にすることが増えています。
この記事をご覧になっているあなたもすでに「BCP対策」というキーワードが気になられたため、インターネットで検索しこのページへ訪問いただいたのではないでしょうか。
そこで、まずは「BCP対策」とはどのようなことなのかを、ここで復習をかねてお互いの考え方を一致させておきたいと思います。
「BCP」とは「Business Continuity Planning(ビジネス・コンテニュイティー・プランニング)」の頭文字を取った略称です。この単語を日本誤訳すると以下のようになります。
「事業継続計画」
これまで地震や台風、水害などによって人的にも設備にも大きな被害が及び、多くの損害を受けたことで
- 事業継続を断念しなくてはならない
- 再開までに長期の時間が必要になる
という状況が訪れました。こうした過去の経験から、できるだけ被害を最小限に留め、災害時にも事業を継続するための方法や手順を、あらかじめ予測想定し計画しておくことを「BCP対策」と呼んでいます。
2: BCP対策が企業に必要な理由
(1)信頼性
ひとつは企業の信頼性を高めるという理由があります。
BCP対策を行っていると、災害が発生した場合でも事業活動が完全に停止することはありません。
災害が発生していないときと比べると生産量やスピードは低下するかもしれませんが、完全に停止することはありませんので、あなたの会社の製品を扱っている取引先へ不便をかけることがかなり減っていくはずです。
突然の災害時でも、損害になる要素を少しでも軽減してくれる会社が取引先であるなら、これは信頼性の向上へとつながることは間違いありません。
(2)地域貢献
災害によって企業が大きなダメージを受けたとすると
- 人員削減
- 事業縮小
- 廃業
このようなシナリオが進んでしまうこともあります。これは単に災害による損失によって会社が無くなるというだけではなく、会社にお勤めされている方の生活基盤を揺るがす問題へと発展します。
また、災害が発生した後、復興するときにいち早く企業が立ち直れると、地域にお住まいの方々へ雇用を創出することができ生活の安定に役立つこともあります。
このように考えるとBCP対策は、会社の事業継続性だけではなく、万が一のときの社会貢献にも関係していることがわかるでしょう。
最近では「SDGs」なども取り上げられるようになっていることからも、企業は自分たちだけの利益を求める活動だけではなく、継続できる社会貢献にもフォーカスし事業を存続させる手段を模索する必要が高まっています。
3: BCP対策における水の重要性
BCP対策について。そしてBCP対策の必要性を見てきました。
次はBCP対策において重要な「水」の確保です。
災害が起こると
- 電気
- ガス
- 水道
ライフラインが停止する可能性が高まります。この中で、私たち人間(ペットも同じですが)が生きていくためには「水」が欠かせません。
これは飲み水が必要というだけではなく、洗う、流すという衛生面において水は大切な要素になってきます。
特に被災地や避難所における衛生面の確保は、伝染病の発生を抑える役割を担っていますし、悪臭による精神面へのケアにも役立つはずです。
また、企業活動を考えると、大型施設や医療施設には大量の「水」が必要になり、水の確保ができないと事業継続が難しい場合もあります。
このようにライフラインが停止しても「水」だけは、私たちが生活する上でも、企業が事業を継続するためにも欠かすことのできないものとなってきます。
4: 災害時における水の確保と対策
(1)確保の状況
これまでの災害時のおける水の確保の状況を参考にすると、次のようになってきます。
災害発生時:断水
災害から2日後:一部復旧
災害から30日後:8割復旧
地域によって復旧の目処は違ってきますが、目安としてはこのような状況になっています。
ここからわかるのは「水」の完全復旧までには時間が必要になるということでしょう。
ということは、普段から「水」に関するライフラインを二重化し災害対策を考えておくことが必要なのです。
(2)節水方法
「水」に関するライフラインの二重化を考えるとき、忘れてはいけないのが「節水」です。
いくら二重化したといっても、完全復旧までには時間が必要ですから、普段と同じように水を使っていては足りなくなります。
そこで災害時には、どの工程やどの業務で水を優先的に使うのかを決めておくことが大切です。
反対に、災害が起こったときには「停止する」業務を決めておくことも重要です。災害が発生してから「どこを止めるのか」を会議している暇はありません。
(3)貯水方法
「水」の二重化の方法として「貯水」という方法があります。
普段から貯水しておくことで、いざというときに使えますので大変安心できる設備だと言えます。
ただし、貯水方法を選ぶ場合には次のポイントには注意しておきましょう。
- 災害時にも耐えられる性能があるのか
- どのくらいの量を貯水できるのか(何日分か)
貯水方法を検討し設置するだけでは、災害時に使えないこともありますので気をつけておきましょう。
(4)井戸水利用
貯水に近い考え方として「井戸水」を活用する方法があります。
井戸は地震にも強いと言われていますので、災害時にも稼働させやすいシステムと言えるでしょう。
また、水道管を通って水が届いているのではなく、地下水脈から水を汲み上げていますので、断水する危険もほとんどありません。
また、災害時だけではなく普段の上水道利用と併用することで、毎月の水道代削減にも役立ちますので、検討する価値のある方法だと思います。
5: まとめ
企業にはBCP対策が求められています。
もし、BCP対策を行っていないのなら、速やかに対策をスタートすることが大切です。
今のまま災害が発生したとき、あなたの会社は取引先や地域住民へ貢献できるでしょうか。
こういった活動が、今後は企業の存続や評価につながっていくことでしょう。
明日から、来週から、ではなく今日から検討をはじめていただきたいと思います。