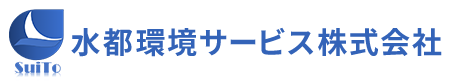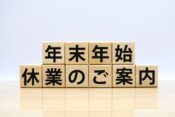災害対策~BCPが病院運営に必要な理由と対策方法~

災害が起こると、一般的なサービスを提供している企業も、病院も一時的に活動を停止せざるを得ない状況になります。
ただ、病院が一般的な企業と違うところは、医療という特殊な活動を一刻も早く復旧し、地域住民や地域企業の復興の助けにならないといけないということです。
そのため、ごく一般的な企業における災害対策の方法だけでは、災害時の病院運営が対応できないこともあります。
そこで今回は、医療という特殊な活動を視野に入れたBCPについて説明していきたいと思います。
1: 病院でBCPが重要な理由
病院でBCPが重要な理由を考えてみましょう。極端な話、一般的なサービスを提供している企業なら、大まかな災害対策だけでも、なんとかなるかもしれません。
しかし病院の災害対策は、かなり考慮しておかないと上手く機能できないこともあるのです。
例えば、災害が発生した場合。病院もまわりの建物と同じように被災する可能性があります。それでもできる限りの病院機能を維持しつつ、患者の診療や地域住民のケガなどを治療しなくてはなりません。
また、入院患者がいる場合であれば、ライフラインが停止しているあいだも、継続的な診療とサポートが必要になりますので、一般的な企業のように「被災したので操業を停止します」ということはできません。
そして、災害が起こった場合、意外に忘れがちですが病院運営に大きな影響を与えるのがスタッフの不在です。
医師や看護師が出勤できない、連絡が取れない。こういったケースも考慮しておかないといけません。
さらに災害の規模が大きくなると、応援医療チームの派遣を要請されることもあれば、派遣を期待していても交通手段が整わず中止になることも考えられます。
病院運営における災害対策はこのように、自分たちの命を守りながらも、できる限りの資源を維持し患者への診療やサポートを継続しつつ、災害で運び込まれてくる新たな患者のトリアージや外科的処置を行わなくてはならないのです。
2: 災害対策としてBCPを病院へ導入するポイント
医療を提供できる場所は、災害が起こると最重要拠点となります。そのため災害が起こったときのことを想定し準備しておかなくてはいけません。
(1)策定体制
病院長や経営責任者が率先してBCP策定を行う体制構築をスタートしなくてはなりません。
放っておいてもBCP策定は進みませんし、外部から提案されたものが100%病院に使えるわけでもありません。
病院長や経営責任者など、自分たちの病院を深く理解している人がリーダーシップを発揮し、各部署や部門から代表メンバーを選定するところから始めましょう。
(2)現状の把握
策定体制を作ったからといって、いきなり行動することはできません。まずはじめに大切なことは現状の把握です。これはBCP策定だけではなく、先生方が普段から行われている医療でも同じことだと思います。
現状の把握なしで、とにかく行動することは合理的ではありませんし、何をどのように準備すれば良いのかもわかりません。
- どの程度の災害まで準備ができているのか
- 指揮命令系統は明確になっているのか
- いざというときの人員確保の方法は整っているのか
- 医療器具や薬品などの保管場所や資材の調達先は明確か
- ほかの医療機関への搬送が必要な場合はどのような手順に従うのか
- 病院全体の耐震性は
- 電気、ガス、水道、通信設備など、ライフラインはどの程度まで耐えられる想定なのか
このようなことを、メンバー全員で洗い出し検証することが大切です。
(3)被害の想定
どのようなフェーズまで被害を想定しているのかを具体的に共有しましょう。
- 災害発生から6時間
- 6時間から72時間
- 72時間から1週間
- 1週間から1ヶ月
- 1ヶ月から3ヶ月
- 3ヶ月以降
それぞれの状況で起こりうる被害状況や、想定される傷病者数を予測しておくことも必要です。
また、災害発生時にもっとも困るのが「夜間の災害」です。勤務しているスタッフが少ないこと。帰宅した医師との連絡が取れなくなることも想定できます。
いつものスタッフが同じだけ病院にいる。という状況ではなく、厳しい状況での想定を意識しておくことで、もしものときにあわてる必要がなくなるはずです。
(4)業務の洗い出し
普段の業務を一度洗い出しておきましょう。この洗い出しによって、通常時に必要となっている資源が明確になってきます。
次に、緊急対応業務の洗い出しも行います。
災害時に必要になると想定できる業務を洗い出すことで、プラスアルファの資源が明確になります。
病院運営には、少し余裕のある資源管理が欠かせません。ここの洗い出しをきちんと行うことは、いざというときの病院の評価につながってくるでしょう。
(5)優先順位を決める
日頃提供している医療サービス。災害時に必要となる医療。なかなか難しいところですが、全部一緒に提供することは、災害時にはできません。
各部門単位で優先順位を決めるのではなく、病院全体として優先順位を設定することで混乱を減らすことができるでしょう。
(6)行動計画を文書にして理解を深める
策定に参加したメンバーだけで「わかった」ではいけません。BCPは病院全体で機能させる行動計画です。
文書にして病院全体で理解を深めましょう。
3: BCPから考えた対応と対策
医療機関の場合、災害時には普段よりも多くの需要が発生します。そのため、普段以上の医療能力に対応できていることが重要。
次の点が対策できているのか検討してみてください。
3.1: インフラ対策
- 建物の耐震性強化は十分か
- 非常電源の確保はできているか
- 非常用給水設備の確保はできているか
- 非常用ガス設備の確保はできているか
- 電話やインターネットなどを使える通信手段は確保できているか
特に医療では、医療機器に多くの電力が必要になります。また、水は清潔な環境を維持するためにも必ず必要になります。
3.2: ライフラインの復旧
病院のある地域は、災害が発生した場合に何日くらいでライフラインが復旧する見込みでしょうか。
3日間で復旧する見込みがあれば、3~4日間利用できる電力や水の設備を整えるのがおすすめです。
例えば、水都環境サービスでご提案させていただいている設備ですと
- 井戸水活用システム
- 水発電機
この2つは、ライフラインが停止したときでもスムーズに代替え設備として活用いただけるでしょう。
井戸水活用システムは、地震にも強いと言われている井戸と地下水を活用した設備なので、災害時に水道管が破裂しても問題なく利用できます。
また、水発電機は「水」または「尿」などによって手軽に発電できる方法です。冷蔵庫や扇風機などにも使える電気を発生しますし、何といってもガソリン式エンジンを使った発電機とは違い、一酸化炭素を発生しないので室内での利用も可能です。
そして医療現場ではできるだけ控えたい「騒音」もありませんし、1台約6kgという軽さなので、災害時でも女性の方が簡単に持ち運べる特徴も備えています。
井戸水活用システムについての詳しい内容はこちらから。
水発電機についての詳しい内容はこちらからご覧いただけます。
4: まとめ
災害が発生しても運営を止められない、または、いち早く復旧しないといけないのが医療現場です。
自分たちの身の安全や家族の安全を気にしつつ、地域への貢献も必要となる混乱した状況ですから、何も決まっていないと正しく冷静に対応できるとは思えません。
ぜひ今回の内容をきっかけにし、あなたの病院が災害の時に一人でも多くの人へ安心を届ける場所になるために、今日から行動していただきたいと思います。