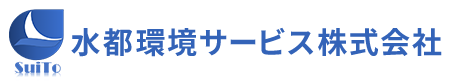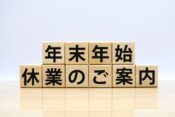災害対策の重要ポイントは「電気」の確保!企業や自治体がやっておくべきこととは

企業や自治体における災害対策の重要性は地域社会や住民から注目されています。
これまで発生した災害を見ると、どのような場合でもスムーズな復旧と共に、復旧までに何ができるのか。どういったことが可能なのかを明確に地域社会へ伝えることの必要性が高くなってきています。
今回は、企業や自治体が災害対策をやっておく理由や、どうして電気の確保が災害対策にとって重要なのかについてお話していきたいと思います。
1: 企業や自治体に災害対策が必要な理由
企業や自治体における災害対策のことを「BCP対策」と呼びます。
「BCP」は
- Business(ビジネス)
- Continuity(コンテニュイティー)
- Planning(プランニング)
の頭文字を取った略で、日本語に訳しますと「事業継続計画」となります。
この計画は災害が発生したときに、被害を最小限に留めるために
- 前もって災害の被害を想定する
- 被害の想定から対策を計画する
- 計画を実行する手順を明確にする
というようなことを行う、リスク管理のひとつです。
では、こういったリスク管理は、企業や自治体にとってどういったメリットがあるのでしょうか。
リスク管理とは「予防」ですから、何も起こらなければ計画に使った費用が無駄になるという考え方もあります。しかし、こういったネガティブな考え方ではなく、ポジティブな考え方でBCP対策を行うと、次のようなメリットがもたらされることでしょう。
- 地域社会からの信頼
- 取引先からの信頼
「無理だと思っていたのに助かった」
「まさか準備していたとは!?」
また、自分たちの企業や自治体の活動そのものも、すでに災害時の対応を計画していますから、あわてておかしな発表をツイートすることもなく、命令系統も明確になっていますので、無駄な時間を使ってあちこちにお伺いをする手間もありません。
スムーズに災害における対応を行うことができるので、結果としては自社や自治体そのものの損害も軽く済むはずです。
2: スムーズな連絡には電気がかかせません
さて、BCP対策の重要性がわかったところで、次は「どうして電気が重要なのか」ということです。
わたしたちが普段使っているライフラインには、電気以外にも、ガスや水道があります。どれも止まると困るのですが、この中でも電気が止まると次のような大変困ったことが起こります。
- 電話が使えないので連絡できない
- スマートフォンの電池がなくなると安否確認ができない
- スマートフォンの電池がなくなると最新情報がわからない
- パソコンが使えないと詳しい情報がわからない
いくらBCP対策を行っていても、いざというとき、企業や自治体からしかるべき人と連絡がとれないのでは、スムーズに計画を進めることはできません。
また、自治体へ地域の企業からサポートの申し入れなどを行う場合でも、お互いに連絡手段が維持できていないと、食い違った見解や、サポートへ向かったのに連絡が入っていないために作業できないという、一般市民から考えると「それはないでしょ」というような事態も起こります。
もし20年前なら、電気がなくても黒電話や公衆電話でやりとりできたかもしれません。しかし今は、みなさんの連絡手段は「スマートフォン」でしょう。
スマートフォンでなくても従来の「携帯電話」でしょうから、常に充電が満たされていないと満足な連絡もできないことになってしまうのです。
これは大変困った状況です。そして、電気の復旧はすぐに終わるのかというと、残念ながら過去の災害時の平均で考えると「1週間」はかかるという想定が必要だと言われています。
いかがでしょう。あなたのスマートフォンや携帯電話、パソコンは1週間電池がもつでしょうか。それも連絡しながら、1週間使えるでしょうか。
おそらく無理だと思います。ですから、BCP対策の中で「電源確保」は大変重要なことになってくるのです。
3: 電気が必ず必要になるところとは
自社や自治体で使わなくても、災害時には必ず電気が必要になるところがあります。
- 病院
- 公共施設
- コンビニ
- 避難施設
こういったところへ一時的に提供することもBCP対策のひとつでしょう。
また、企業であれば、
- 工場
- 社宅
などで活用することで、従業員の方々や家族の方に安心を提供することもできます。
こういった災害復旧中の電源確保は、大変有意義な地域貢献になります。
被災状況によっては、確保した電源を自社の工場へ配置し、地域住民の方を企業の施設へ受け入れ、スマートフォンの充電や、熱中症対策にも役立てることができます。
4: BCP対策として自家発電機をどう選ぶのがベストか
最後に、BCP対策として自家発電機を選ぶポイントを見ておきましょう。そして、すべてのポイントを満たしてくれる自家発電機を選ぶようにしておきたいですね。
(1)消費電力
自家発電機によって使える電力量が違います。あなたが想定している消費電力量にあったものを選びましょう。
(2)持ち運べるか
災害時に持ち運べると、サポートできることにバリエーションが生まれ、状況に適した対応を進めやすくなります。
重くても大人二人で運べるくらいのものが良いでしょう。車やクレーンがないと運べないものでは、災害時に重機が手配できない可能性が高いため使えないこともあります。
(3)燃料が手に入りやすい
自家発電機には、電気を生み出すための燃料が必要になります。
一般的には
- ガソリン
- ガス
- 太陽光
- 水
- 人力
このようなエネルギー源を使うタイプがあります。
消費電力や使う場所、燃料の入手方法を考えて選びましょう。
(4)室内でも使える
自家発電機は屋外で使うことが多いですが、梅雨時期などは屋内で使えた方が便利です。
また、病院などで使う場合は屋内で使えるものが重宝します。
(5)静かである
自家発電機は夜も使うことがあります。
また、被災して疲れている人の近くで使うこともあります。
こういった状況で、自家発電機の大きな音で更に疲れを増してしまっては、体だけでなく心の平穏も脅かすことになりかねません。
できるだけ、一般市民として聞いたときに「静かだな」と感じられるものを選ぶようにしておきたいですね。メーカーの測定数値では感覚が違います。
(6)安定して発電できる
スマートフォンなら同時に100台くらいは充電できる安定性がほしいですね。
このようなポイントがあるのですが、すべてのポイントを満たしている発電機はというと、、、「水を使った発電機」になります。
ガソリンやガスを使った発電機は騒音が出やすいですし、排気ガスも出ますので室内で使うのは難しいです。また、災害時に燃料となるガソリンやガスが手に入るのかという不安要素もあります。
太陽光発電の場合なら騒音はありませんし、室内でも使えます。燃料となる太陽光はいつでも手に入りますが、夜や曇っているときには電力が安定しません。
しかし、水を使った発電機なら
- エンジンで発電していないので静か
- 排気ガスも出ないので室内で使える
- 重さも6kgほどなので移動が楽
- 水が燃料なのでどこでも手に入る
- 仮に災害で水が手に入らない場合でも「尿」で発電できる
- スマートフォンも100台なら余裕で充電できる安定性がある
このように、必要なポイントをすべて網羅できてしまいます。
もしあなたがここまでお読みになった結果、水を使った発電機に興味を持たれたのであれば、こちらをクリックしてください。詳細な内容を専用ページにご用意させていただいております。
5: まとめ
災害対策には「電気の確保」が重要です。電気がないと連絡すらできない時代ですから、安心できる状況を維持するためには、自家発電機の準備をしておくことが大切です。
今回の内容を参考にし、あなたの企業や自治体での災害対策を進めてください。