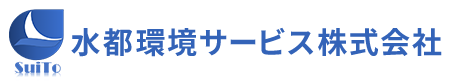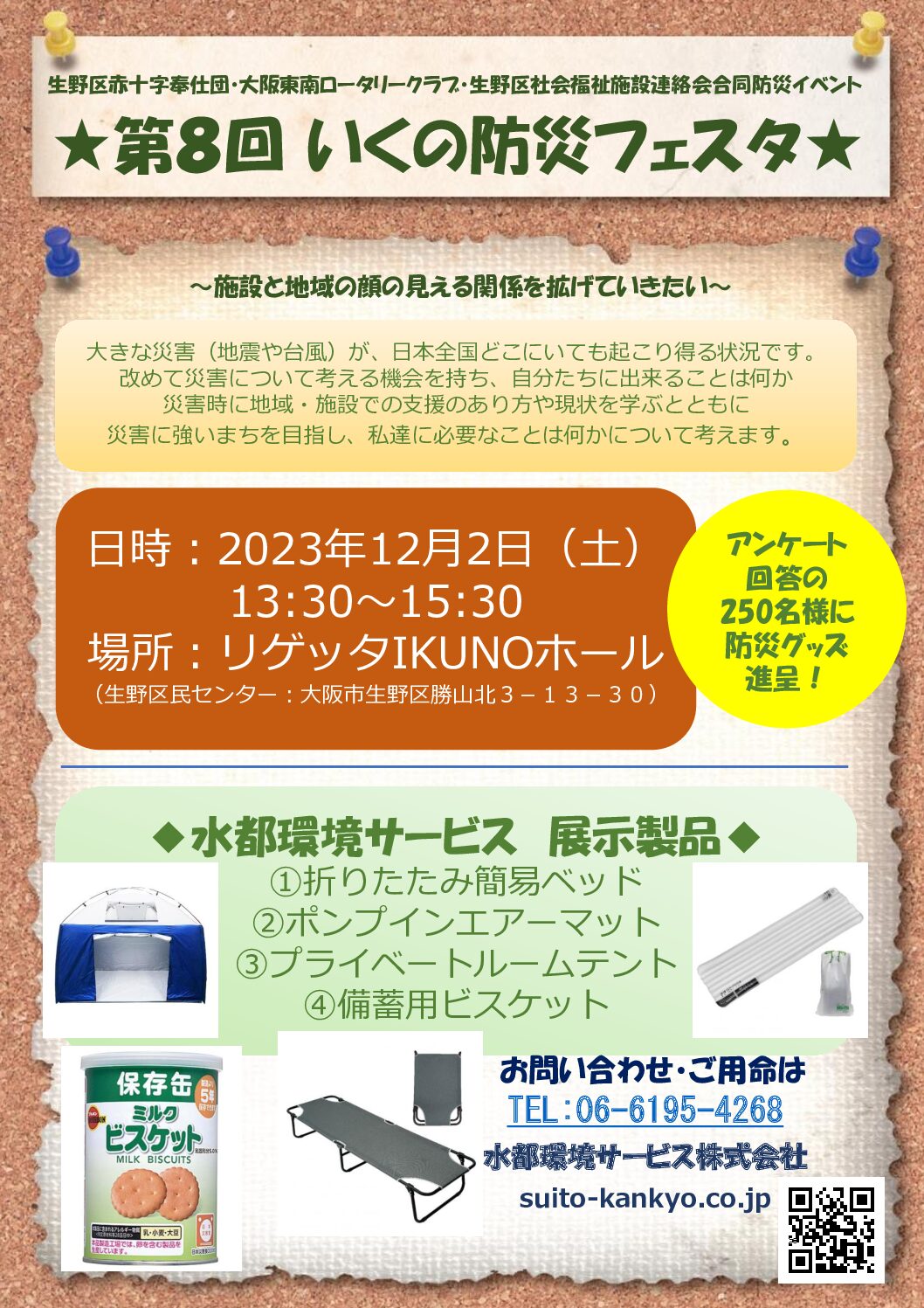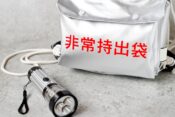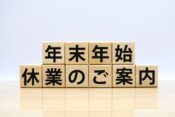災害でも発電機や蓄電池で安心!家庭用の停電対策を考えよう

昨今の自然災害を考えると、会社や工場、自治体だけではなく家庭での停電に備えて何らかの対策をしておくことが大切です。
そこで自家発電を思いつく方が多いのですが、意外にも自家発電には種類があります。そして種類があるということは、それぞれに特性や特長があるということです。
また、あなたのお家で使う電力や、地域での対策方法や設備によっては自家発電機ではなく電気を蓄めておく「蓄電池」が有効な場合もあります。
今回は、もしものときに「電気」を安心して使えるようにしておく方法を紹介していきます。
目次
1: 災害時に発電機や蓄電池が家庭に必要な理由
地震や台風、大雨による土砂災害などによって生活の基盤でもあるライフラインがストップすると、生活を続けることが難しくなります。
特に「電気」は「水」「ガス」のように、家で備蓄しておくことが簡単ではありません。
水ですと、災害用にペットボトルのミネラルウォーターを購入しておけば何とかなります。
ガスに関しては、カセットコンロとカセット式のガスを用意しておけば、これも2~3日はしのげるでしょう。
しかし「電気」は、特別な装置がないと備蓄しておくことができません。
もし備蓄していない場合は、スマートフォンやパソコンを使おうとしても、バッテリーに残っている電気だけを慎重に使うしかありません。
生活に必要となる冷蔵庫や災害情報を知る術でもあるラジオ、電子レンジも使うことができません。
最近では固定電話も電気がないと通話できませんので、携帯電話しか使えないということもあるでしょう。
一般的に災害時には、このような状態が3日~4日は続くと言われていますから、電気がないと安否確認をするために必要なスマートフォンの電池も0%になる可能性が出てきます。
このような中で、簡易的な復旧や、近くの施設で充電できるようになったり、食料が届けられるようになったりするまでのあいだ、安全に安心して連絡を取り合い過ごすためには、もしものときに家庭で電気が使える状態に対策しておくことが必要です。
2: 災害時に家庭で使いやすい発電機や蓄電池とは
災害時に家庭で使いやすい「電気の元」としては、自家発電機や蓄電池があります。
それぞれに種類があり、特性も違ってきますので、あなたのご家庭でどのように使用できるのかを考えていただきたいと思います。
2.1: 使える電気の目安を知っておこう
まず大事なことは、自家発電機でも蓄電池でも、もしものときに家庭で使いたい家電に必要な電気量の目安をチェックしておきましょう。
いくら値段が安いからといって、使える電力量が小さいものであった場合、いざというとき、安心して使うことができません。
携帯電話やスマートフォンの充電は必須になるでしょう。
LED式のランプや照明が必要かもしれません。
冬なら暖を取るための家電。夏なら扇風機はほしいところです。
小さなお子さんがいらっしゃるご家庭や、体に障害をお持ちの方、病気療養中の方がいらっしゃる場合であれば、必要になってくる電力量も変化します。
3日~4日は安心して暮らせるために最低限必要となる電力量をチェックしておくことが重要です。
2.2: 発電機の種類と特徴
それでは自家発電機の種類と特徴を順に見ていきましょう。
(1)手動式発電機
燃料のいらない発電機です。
手や足でハンドルやペダルを回すことで発電できます。
人力で発電できますので、どんな状態でも電気が手に入るのがメリットと言えるでしょう。
いっぽう、手動式なので発電量が少ないため、小型の電気製品には使えますが、大きな電力が必要な製品には不向きだといえます。
他の発電機のサブとして、小型電気製品専用としておすすめです。
(2)ガソリン発電機
名前のとおり、ガソリンを使って発電する機械です。
発電量は商品によって変わってきますので、あなたの家庭に必要な電気量を満たしてくれるものを選びましょう。
ガソリン発電機は燃料となるガソリンさえあれば、勝手に発電してくれますので大変楽ではあります。また、インバーター式の発電機なら安定した良質の電気を供給してくれるので、スマートフォンやパソコンなどにも安心して使えます。
このようにガソリン発電機は、ここ一番に楽なのですが次のようなデメリットもあります。それは、
- 発電しているときは騒音でうるさい
- 室内や締め切った状況では使えない
災害時に騒音を出して自家発電していると、まわりからの「やっかみ」にあう可能性もあります。当然「うるさい!」と怒鳴り込んでくる人もいるでしょう。
ガソリン発電機は、オートバイのエンジンを回しているのと同じですから、いくらカタログ上は「静音」と謳われていても、市民感覚としては騒音であることは間違いありません。
(3)カセットボンベ発電機
カセットコンロのボンベを使った発電機です。
燃料であるカセットボンベは保管しやすいので災害時にも使いやすいですね。
ただし、カセットボンベ発電機もガソリン発電機と同じように、音がうるさいというデメリットがあります。
そして、ここが困ったところですが寒冷地など気温が下がりすぎるとガスが使えなくなり発電することができません。
(4)ソーラー発電機
音もなく太陽だけあれば電気が作れます。ただ、ソーラー発電機は電力量が少ないですから、小型電化製品に使うことを考えましょう。
(5)水発電
あまり知られていませんが、水を使うことで発電できる装置があります。この装置は、水だけではなく、尿を使っても発電できますので災害時でもかなり安心です。
水都環境サービスが扱っている「水発電機」は、重さが6kgなので女性の方でも持ち運び可能。電力量も十分にありますので、スマートフォンだけなら4,000台以上をフル充電することもできます。
水発電機に興味がありましたら、こちらのページで詳細を掲載しておりますのでご覧ください。
2.3: 蓄電池の種類と特徴
蓄電池は自分で発電することはできません。その代わりに電気を蓄めておくことができます。
(1)モバイルバッテリー
スマートフォンやタブレットなど、情報収集のための機器に使いやすいのがモバイルバッテリーです。
最近は低価格でありながら、バッテリー容量が大きいものも出てきているため、かなり扱いやすい製品だと言えます。
20,000mAhのモバイルバッテリーを満充電しておくと、10回くらいはスマートフォンを充電できますので3~4日程度は持ちこたえることができるでしょう。
(2)インバーターバッテリー
家庭用の電化製品に使えるインバーター内蔵バッテリーもあります。
これなら、スマートフォンだけではなく、小さな家電にも使えます。
(3)電気自動車
電気自動車は災害時の電源としても使えます。
消費電力の大きな家電でも動かせますので安心です。
もし電気自動車をお持ちなら、普段から非常用の電源として充電しておきましょう。
3: まとめ
災害における家庭用の停電対策を紹介しました。
主に家庭で扱いやすいのは、発電機や蓄電池ということになります。
発電機の場合は、それぞれに特性がありますので、どのような使い方をするのか考えてもらいたいと思います。
特に騒音対策や二酸化炭素対策は、対応を怠るとトラブルの原因にもなりかねませんので、慎重に検討しておく必要があるでしょう。