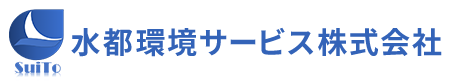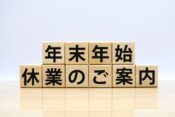ウイルス対策でオゾンは安全?人体への影響や注意点を解説!

ウイルス対策として、高い除菌力を誇るオゾンが注目されています。
ただ日常生活において、あまりオゾンを利用する話を聞かないことから、人体への影響はないのか、気になるという方もいるでしょう。
今回は、オゾンは安全なのか人体への影響や注意点について紹介していきます。
目次
1.オゾンによる人体への影響
ウイルス除菌としてオゾンを活用する場合、オゾンは除菌力に優れているためウイルス対策として効果が期待できます。
またウイルスを分解することで、オゾン自体は酸素になることから、人体や環境への影響はほとんどないと言えるでしょう。
ただオゾン濃度によっては、注意しないといけないと産業衛生学会・許容濃度委員会が公表しています。
オゾンガスの労働環境における抑制濃度として規定されているのは、8時間以内であれば0.1ppm、8時間以上であれば0.07ppmが限度です。
食品工場の殺菌作業の場合には、1~5ppmまでが抑制濃度とされていますが、この時は人間が立ち入ることは禁止されています。
・オゾンガスの人体に及ぼす悪影響
| 0.02~0.05ppm:数秒で特有のニオイがわかる |
| 0.1~0.3ppm:数分~数十分で鼻、喉の刺激がある、ぜんそく患者の発作回数が上昇する |
| 0.23ppm:労働者に慢性気管支炎などの有症率が増加する |
| 0.6~0.8ppm:2時間で胸痛、咳、呼吸困難などの症状が見られ、気道抵抗の増加、肺ガス交換の低下などがある |
| 1~2ppm:1~2時間で疲労感、頭痛などを感じる |
| 10ppm:数十分で呼吸困難、肺水腫、昏睡状態になることがある |
| 15~20ppm:約2時間で肺水腫で死亡することがある。 |
| 1,000ppm:1,000ppmを超えたレベルでは数分で死亡することがある |
2.オゾン濃度を管理するCT値
ウイルス対策として、オゾンを利用することは、除菌力を考えると理想的です。
しかし濃度が高すぎると、人体への影響があることはわかっています。
その際に、オゾン濃度を管理するために「CT値」を理解しておくことが大切です。
CT値は、国際的に認められている指標で、殺菌・不活性効果を示す値となっています。
オゾンガス濃度と時間の積を表しており、CT値が高いほど効果は増加し、CT値が低いほど効果は低下するのが特徴です。
CT値でオゾン濃度を数値化し、管理することで安全を考慮した上で、ウイルスを除菌したり、十分な脱臭効果を得ることができます。
3.CT値積算機能付きオゾン発生器「オラくりんCT」
ウイルス対策としてオゾン発生器を使用したいが、オゾン濃度が気になるという方は、CT値積算機能付きの「オラくりんCT」がおすすめです。
「オラくりんCT」を活用すれば、CT値が見えるのでオゾン濃度が管理しやすくなります。
具体的には、どのような特徴を持っているオゾン発生器なのか紹介していきましょう。
・オゾンガスの処理効果が数値化
オゾンガスによる除菌・脱臭効果がどれほど出ているのか、数値化できるのが「オラくりんCT」の特徴です。
結果が見えることで、目的に応じてウイルス対策を実施することができるので、効率よく除菌することができます。
・CT値積算機能により同設定で再現可能
CT値積算機能が搭載されていることにより、除菌・脱臭効果が表れている設定をいつでも再現することが可能です。
それに伴い、同じ処理効果を生み出すことができるので、毎日安全にウイルス対策を講じることができます。
・オゾンガス濃度計と経過時間表示機能付き
オゾンガス濃度をリアルタイムで表示される機能が搭載されているので、現在のオゾン濃度を把握した上で、安全に管理することができます。
また運転中の処理経過時間も表示されるので、どれくらいの運転時間でウイルス除菌できたのか把握することが可能です。
・持ち運びが便利
「オラくりんCT」の重量は8kgとなっていることから、持ち運びしやすい設計となっています。
取っ手もついているので、部屋を変えて稼働させることも可能です。
・業務用ハイスペック機器
オゾンガスは2,000mg/hまで発生させることができます。
ただ濃度が高いと、人体への影響が懸念されるので、CT値と照らし合わせて、適切なオゾン発生量を調節することが大切です。
また180㎥/hの循環ファンが搭載されているので、広範囲の除菌・脱臭を実現することができます。
・オゾン回収機能付き
室内にオゾンが残されているままでは、人体への影響や独特のニオイが気になるというケースがあります。
問題を回避するために、「オラくりんCT」ではオゾンガス濃度が0.1ppmになるまで自動回収する機能が搭載されているので安心です。
4.オゾンでウイルス対策を実施する際の注意点
オゾン発生器でのウイルス対策は、短期間で除菌・脱臭効果が期待できるため、効率の良い方法だと考えられます。
ただ使用する上では、いくつか注意すべき点があるので、事前に把握しておきましょう。
・高濃度のオゾンで腐食する物質
日常生活で利用する物質の中には、オゾンに触れることで腐食してしまうことがあります。例えば、ゴムやプラスチックなどです。
ゴムやプラスチックで出来た物が室内にある状態で、オゾン発生器を利用すると、オゾン濃度次第では腐食してしまう恐れがあります。
低濃度であれば問題はありませんが、人がいない状態で高濃度のオゾンで除菌・脱臭したいという時には、扱いに注意する必要があるでしょう。
・オゾン特有のニオイ
オゾンは低濃度でも、特有のニオイを感じることがあります。オゾン発生器を利用している際にも、特有のニオイを感じることがあるので、出来るだけ換気をした上で稼働させた方が良いでしょう。
オゾン発生器の濃度であれば、問題はないと思いますが、オゾン濃度が高いと、ニオイが強くなり、気分が悪くなることもあるので、稼働させる際は注意が必要です。
5.基本的にオゾン発生器で人体への影響はほとんどない
オゾンによる人体への影響について紹介しましたが、基本的にはオゾン発生器では人体への影響はほとんどありません。
低濃度での設定や換気を行っていれば、体調が変化することはないでしょう。
ただウイルス対策として、濃度を上げて稼働させる際には、出来るだけ人はいない状態で稼働させることが大切です。
特に人体への悪影響はほとんどありませんが、特有のニオイは低濃度でも感じることがあります。
より安全に、オゾン発生器を利用するためにも、人がいない時に効率よく除菌する方法を取りましょう。
中には低濃度のオゾンを24時間稼働させることで、部屋の除菌・脱臭を行うオゾン発生器もあります。
その場合は、人体への影響は一切ないので、安心して毎日のウイルス対策として利用することができるでしょう。
6.新型コロナウイルスの影響によりオゾン発生器の重要性が高まる
新型コロナウイルスの影響で、日本全国で緊急事態宣言が発表されました。
ただ自粛が続いた結果、感染者の数が減ったということもあり、一部を除き、緊急事態宣言は解除される方向になっています。
緊急事態宣言が発表されたからといって、新型コロナウイルスの感染リスクが下がった訳ではないので、オゾン発生器の重要性が高まりつつあるのです。
特に飲食店・病院・介護施設・教育施設などでは、人が集まりやすい環境下にあるので、早めにオゾン発生器を導入することが求められるでしょう。
7.CT値がわかるオゾン発生器で安全にウイルス対策
今回紹介した「オラくりんCT」は、CT値がわかるオゾン発生器であるため、オゾン濃度をしっかり管理した上で、除菌効果を確認することができます。
正しく活用すれば、安全にウイルス対策を実施することができるでしょう。
今後は、さらにウイルス対策が求められてくることが想定されるので、人が集まりやすい施設では、早めの導入が肝心です。
詳しい内容は下記のURLからもご確認いただけますので、オゾン発生器の購入を検討している方はぜひ一度覗いてみてください。
https://suito-kankyo.co.jp/ozone/
https://peraichi.com/landing_pages/view/bt-180h-suitokankyo